元住宅営業マンとして約34年間、ハウスメーカー・工務店・不動産開発の現場に携わってきました。
本記事は、営業現場と自宅建築の両方を経験した筆者が、実務経験に基づき家づくりに関する判断材料となる情報を提供することを主な目的としています。
記事内にはPR・アフィリエイトリンクを含む場合がありますが、特定の商品やサービスの購入を推奨・強制するものではありません。
こんにちは。
元住宅営業マンまめおやじです。
新築を建てる際、「照明や外構は自分で手配した方が、安くておしゃれになるのでは?」と考えたことはありませんか?
ご自身で建材や業者を手配する「施主支給・施主手配」は、うまく活用すればコストを抑え、理想の家を実現できる有効な手段です。
しかしその一方で、建築会社との連携がうまくいかないと、予期せぬトラブルや追加費用が発生するリスクも潜んでいます。
本記事では、元住宅営業マンの視点から、よくある失敗例を交えつつ、後悔しないための「成功のコツ」を分かりやすく解説します。
- 新築やリフォームでコストを抑えたいと考えている人
- 施主支給や施主手配を検討しているけれど、不安や疑問がある人
- 住宅会社に全部任せるのではなく、自分のこだわりを取り入れたい人
- 実際にあったトラブル例や成功例を参考にして、安心して家づくりを進めたい人


1. 「施主手配とは?」基本を押さえよう

■結 論
施主手配とは、ハウスメーカーや工務店を通さずに、施主(=あなた)が自ら業者や製品を手配・契約することです。
■カンタン解説
新築住宅を建てる際、通常は住宅会社が照明・エアコン・外構などを一括して管理・施工します。
しかし、「もっとコストを抑えたい」「こだわりの商品を選びたい」という理由で、施主自身が一部の工事や設備を外部業者に直接依頼することがあります。
これが「施主手配」と呼ばれる方法です。
自由度が高く、費用も抑えられる可能性がある反面、スケジュール調整や責任の所在が複雑になりやすく、知識がないまま進めるとトラブルになるリスクもあるので注意が必要です。
■元住宅営業マンのひとこと

自由=自己責任。
良くも悪くも、自分でやるという選択にはリスクが伴います。だからこそ、しっかり準備して進めましょう。
2. 「施主手配できる主な項目リスト」
「施主手配」と一口に言っても、対象になる項目は意外と幅広く、すべての工程を自分で管理する必要はありません。
以下は、施主手配でよく扱われる代表的な項目です。
■施主手配しやすい代表項目一覧
| 項目 | 説明例・備考 |
|---|---|
| 照明器具 | ダウンライト、シーリングライトなど |
| カーテン類 | オーダーカーテン、ロールスクリーン等 |
| エアコン | 家電量販店やネットでの購入が一般的 |
| 家具 | ソファ、ベッド、ダイニングセット等 |
| 家電 | 冷蔵庫・洗濯機など生活必需品 |
| 外構工事 | フェンス・門柱・アプローチなど |
| 通信・配線工事 | インターネット回線やテレビアンテナなど |
| その他設備品 | 宅配ボックス、表札、防犯カメラなど |
このように、設備や工事の一部を施主自身が選んで手配することで、こだわりを実現したり、コストを抑えることが可能です。
■元住宅営業マンのひとこと

全部を施主手配しようとせず、こだわりたい部分だけ選ぶのが成功のコツ。
予算と手間のバランスを見極めましょう。
3. 施主手配に向いているもの・注意が必要なもの
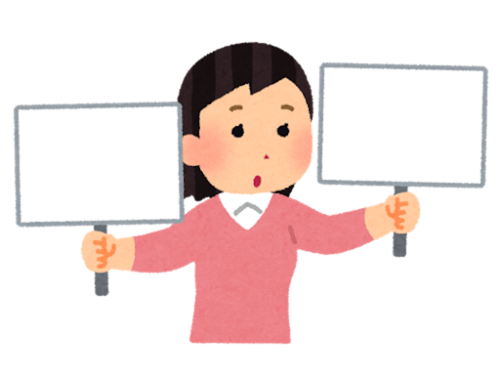
一般的に、施主手配の難易度はアイテムによって異なります。
比較的チャレンジしやすいもの(初心者向け)
- 取り付けが簡単なもの: 照明器具、スイッチ・コンセントプレート、タオル掛け、ペーパーホルダー、カーテンレール、表札、ポストなど。
- 理由: 専門的な工事が不要、または軽微なものが多く、サイズ違いなどのトラブルが起きにくい。
慎重な検討が必要なもの(上級者向け)
- 専門工事が必要で、建物と一体化するもの: キッチン、ユニットバス、トイレ、洗面化粧台、食洗機、給湯器など。
- 建物の性能に関わるもの: 玄関ドア、サッシ、フローリングなどの建材。
- 理由: 給排水や電気工事、下地工事が複雑に絡み、サイズや仕様の確認が非常に重要。不具合が起きた際の保証問題もシビアになりがちです。
施主支給は、家づくりへの愛着を深め、コストを抑えながら理想を追求できる素晴らしい方法です。
しかし、成功のためには施主自身にも相応の知識と手間が求められます。
■元住宅営業マンのひとこと

施工会社を家づくりのパートナーとして尊重し、十分なコミュニケーションを取りながら進めることが、最高の住まいを実現するための鍵となるでしょう。
★「施主手配」についてはこちらの記事もご覧ください。
4. 施主手配で失敗するポイント

大きく分けると4つに分類されます。
- ハウスメーカー・工務店との連携不足
- 製品知識の不足と発注ミス
- 保証・責任の所在が曖昧になる
- 住宅ローンが使えない場合がある
1.ハウスメーカー・工務店との連携不足
最も多い失敗が、施工会社との連携がうまくいかないケースです。
- ありがちな失敗
- 相談なしに勝手に商品を発注し、後から「取り付けできません」と断られた。
- 支給品の納期が遅れ、工事全体のスケジュールが大幅に遅延してしまった。
- 施工会社から別途、高額な「取り付け費」や「保管料」を請求され、結果的に高くついた。
- そもそも施工会社が施主支給を快く思っておらず、関係性が悪化してしまった。
2.製品知識の不足と発注ミス
デザインだけで選んでしまい、設置条件などを確認していなかったために起こる失敗です。
- ありがちな失敗
- ネットの写真だけで照明器具を選んだら、思ったより安っぽく、部屋の雰囲気に合わなかった。
- 海外製の食洗機を選んだが、日本の電圧に対応しておらず電気配線工事が追加になった。
- 洗面ボウルのサイズがカウンターの開口寸法と合わず、取り付けられなかった。
- 部品を決めるのが完成間際になり、現場監督から下地が必要と言われて、仕方なく別のものを再度注文した。
3.保証・責任の所在が曖昧になる
製品に不具合が起きた時、それが「製品自体の初期不良」なのか「施工ミス」なのか原因の切り分けが難しく、責任の所在で揉めるケースです。
- ありがちな失敗
- 入居後すぐに支給した給湯器が故障。メーカーは「施工の問題」、施工会社は「製品の問題」と主張し、修理が進まない。
- 配送中に商品が破損していたが、受け取り時の確認を怠り、保証が受けられなかった。
- 結局、施主が泣き寝入りする形で修理費用を全額負担することになった。
4.住宅ローンが使えない場合がある
施主手配品は住宅ローンとして扱われる建物本体費用として認められない場合があります。事前に金融機関の確認が必要。住宅ローン扱いにならない場合、自己資金での支払いになるため、要注意。手配先の支払い期限も事前に確認しておきましょう。
■元住宅営業マンのひとこと

「連携不足」が失敗の原因のほとんどです。不具合があった時は保証は難しいと思っておくほうがいいでしょう。
5. 施主手配で成功するポイント

理想の住まいを実現するための「成功するポイント」を詳しく解説します。
成功への対策【住宅会社】
- 契約前の段階で確認する: 施主支給を検討している場合、必ずハウスメーカーや工務店との契約前にその旨を伝え、対応可能か、どこまでの範囲ならOKかを確認しましょう。
- 対応に前向きな会社を選ぶことが大前提です。
- 「報・連・相」を徹底する: 支給したい製品の「品番」「仕様書」「図面」を早めに共有し、設置に問題がないかを確認します。
- 発注後も納期を正確に伝え、工事スケジュールに組み込んでもらいましょう。
- 費用について書面で確認する: 製品代以外にかかる費用(送料、取り付け費、諸経費など)の有無や金額を事前に確認し、見積もりや合意書に明記してもらいましょう。
成功への対策【施主手配品を選ぶ】
- ショールームで現物を確認する: 写真やカタログだけでなく、できるだけショールームに足を運び、実物の色合い、質感、サイズ感を確認しましょう。
- 仕様書・施工説明書を読み込む: 購入前に製品の仕様書や施工説明書を施工会社の担当者と一緒に確認し、設置条件(電源、給排水の位置、下地の要不要など)を満たしているかチェックします。
- プロに相談する: 不安な点は、施工会社の担当者や、支給品を購入する店舗の専門スタッフに相談し、アドバイスを求めましょう。
成功への対策【施主手配品の保証等】
- 保証範囲について合意書を交わす: 「製品の保証は施主(メーカー保証)」「施工に関する保証は施工会社」というように、責任範囲を明確にした合意書を書面で交わしておくことが重要です。
- 荷受けは慎重に行う: 商品が届いたら、すぐに施工会社の担当者立ち会いのもとで開梱し、傷や破損、部品の不足がないかを確認しましょう。問題があればすぐに購入元へ連絡します。
- 信頼できる購入先を選ぶ: 保証がしっかりしている、万が一の際に迅速に対応してくれる信頼できる店舗から購入しましょう。
■元住宅営業マンのひとこと

とにかく早めに部品を決めて、住宅会社と取りつけ・納品方法について詳しく打合せする、これが全てです。
6. 【実例】筆者の施主手配の成功事例
成功事例①:ネットで購入した照明器具をうまく導入できたケース
新築時、施主がこだわって選んだデザイナーズ照明をネットで購入。住宅会社に事前相談し、「器具の取付方法・重さ・配線図」などを共有しておいたことで、現場でもスムーズに設置が完了。
結果、コストも抑えられ、希望のインテリアも実現できた。
👉 ポイント:
「住宅会社に早めに相談し、製品情報を細かく伝えたことが成功のカギ」
成功事例②:外構を施主手配で予算内に収めたケース
建物の設計段階から外構業者が決定済。建築時から給排水の桝位置やGL(高さ)について住宅会社とすり合わせしておいたため、外構工事に入ってからのズレもなく、予算内で理想の外構工事が完成。
👉 ポイント:
「設計段階から外構を意識して準備し、情報共有ができていた」
■元住宅営業マンのひとこと

「成功した方の多くは、“住宅会社との連携”を軽視していません。
7. 【実例】筆者の施主手配の失敗事例
失敗事例①:施主手配の解体屋がご近所トラブル
施主手配で解体工事を手配。工事前に挨拶もせず、養生シートも適当に設置で、早朝から解体がはじまり、ご近所トラブルに。
👉 原因:
「安いなりには理由があります。品質の低い仕事の見積は安いです」
失敗事例②:当初の外構金額から大幅に金額がアップになった
設計段階で施主が外構業者から、図面見積をもらう。その後住宅会社との打ち合わせで地盤高さ(GL)が変更に。建物完成後、改めて高さを測り、当初の計画と違うため、追加金額の請求が請求された。
👉 原因:
「地盤の高さが変更になった情報が外構業者へ共有されていなかったことが原因」
■元住宅営業マンのひとこと

失敗したケースは“自分で手配すれば安く済む”という思い込みが原因になっていることが多いです。
施主手配は、プロの現場の流れを理解した上でうまく組み込むことが最大のポイントです。」
7. なぜ住宅会社は施主手配を嫌がるのか?

■結 論
- 「工事スケジュールが狂う」
- 「打合せの手間が増える」
- 「手間・責任が増えるのに報酬がない」
- 「クレームリスクが上がる」
■カンタン解説
1. 工程遅延による全体スケジュールへの影響
住宅会社は工期を厳密に管理しています。そこに施主手配の業者が割り込むと、「いつ来るか分からない」「来たけど対応できない」などでスケジュールが崩れるリスクがあります。
2. 不慣れな製品・業者への対応負担
施主が選んだ設備や業者に対し、住宅会社側は情報もノウハウもないため、その場しのぎの対応を迫られることも。これが事故やクレームの原因になります。
3. 保証対象外となる恐れ
手間が増えた割に利益も少なく、不具合になった場合、保証対象外になると、もめる可能性が高いです。
■元住宅営業マンのひとこと

「正直に言えば、手配されたものに対して文句は言えないけど、責任も取れない。それが“嫌がられる”本音です。」
8. まとめ
施主手配は「こだわり」と「自己責任」のバランスを見極めが大事。
施主手配は、コスト削減や理想の家づくりを実現する強力な手段です。
ただし、それには綿密な準備・知識・住宅会社との事前調整が不可欠です。
■要点まとめ
- 施主手配は一部設備や工事を自分で手配する方法
- 自由度が高いが、トラブルのリスクも同時に高くなる
- 住宅会社との関係性・保証・工事工程の調整が重要
- すべてを手配せず、“こだわりたい箇所だけ”に絞るのがコツ
「安く仕上げたい、理想の設備を入れたい…その気持ちはよく分かります。
でも、住宅はチーム戦。1人で進めるには限界があります。
うまく住宅会社と連携しながら、納得できる住まいを目指しましょう。」
家づくりは正解が一つではありません。
本記事の内容が、後悔のない判断をするための参考になれば幸いです。
筆者の考え方や立ち位置については
当ブログについて
にまとめています。
ここまで読んで頂きありがとうございました。
貴方にとって良い一日を~まめおやじ




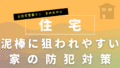
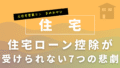
コメント