元住宅営業マンとして約34年間、ハウスメーカー・工務店・不動産開発の現場に携わってきました。
本記事は、営業現場と自宅建築の両方を経験した筆者が、実務経験に基づき家づくりに関する判断材料となる情報を提供することを主な目的としています。
記事内にはPR・アフィリエイトリンクを含む場合がありますが、特定の商品やサービスの購入を推奨・強制するものではありません。
こんにちは。元住宅営業マンまめおやじです。
家を建てる際、意外と見落としがちなのが「窓の配置」。
特に住宅密集地では、隣家との距離や視線の問題が後々のトラブルに発展することもあります。
今回は、実際に経験した隣家との窓トラブルをもとに、事前に防ぐためのポイントや法律の知識について解説します。
- 施工会社が決まって打合せ中の人
- これから家を検討している人
- これから着工する人


1. 家づくりにおける隣家との関係性の重要性
家を建てる際、多くの人がデザインや間取りにこだわりますが、実は「窓の配置」も非常に重要な要素です。
特に住宅密集地では、隣家との距離が非常に近いため、窓の位置によってはプライバシーが丸見えになってしまうこともあります。
このような問題が原因で入居後にトラブルが発生するケースは少なくありません。
実際に隣家とのトラブルで最も多いのが「視線問題」です。
お互いの家の窓が向かい合ってしまった場合、プライバシーの侵害や、洗濯物や室内が見えてしまうといった問題が生じることがあります。
例えば、隣の家の窓と自宅の窓が正面に向き合ってしまうと、意図しない視線を受けてしまうことになります。
また、洗濯物を干す場所が隣の家の窓から見えてしまうこともあります。
これらの問題を事前に防ぐには、設計段階で隣家の状況を考慮し、窓の配置を工夫することが大切です。
2. 実際にあった隣家との窓トラブル
.png)
ある新築分譲地での出来事です。角地に建てる施主様と契約になり、ある新商品の住宅を建築することになりました。
しかし、工事が進む中で隣家の住人からクレームが入ったのです。
「お宅の二階の窓がうちの窓と向かい合っているんですけど!」
確かに、隣家の窓と施主様の家の窓は向かい合っていました。
隣家側が境界から約1メートル、こちら側は約1.5メートルの位置。
法的には境界から1メートル以上の距離があり、問題はありませんでした。
ですが、隣家の方は「うちが先に建てたのだから配慮すべきだ」と主張し、窓の位置を変更するように求めてきたのです。
その後、施主様と相談し、窓の変更は行わずに決着しました。
結果的には隣家の要求は通らなかったのですが、このようなトラブルは決して珍しいものではありません。
隣家とのトラブルは、視線やプライバシーの問題だけでなく、時には感情的なものにもなることがあります。
3. 法律から見る窓配置のルール
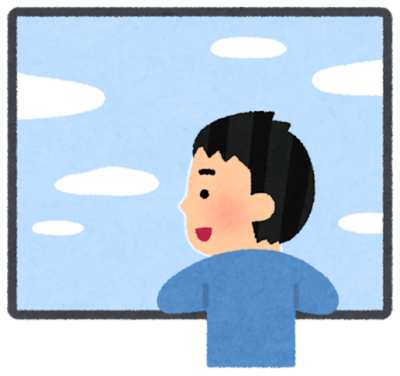
窓の配置に関する法律には一定のルールがあります。特に重要なのが民法235条の「目隠し請求権」です。
この規定は、隣家との窓の配置についてのルールを定めており、プライバシーを守るための措置として、目隠しの設置を求めることができる権利を規定しています。
3-1.境界から1メートル未満にある窓には目隠しが必要
目隠しの設置義務が生じるのは、境界線から1メートル未満の窓です。
この場合、目隠しとしてアルミやステンレス製のしっかりとした壁やフェンスを設置する必要があります。
3-2.1メートル以上の距離があれば基本的に問題なし
1メートル以上の距離があれば、基本的には窓の配置に問題はありません。
したがって、法律的には今回のケースのような1メートル以上の距離があれば、問題は生じにくいということになります。
しかし、法的に問題がない場合でも、実際には隣家との間でトラブルが生じる可能性があることも理解しておく必要があります。
4. 後悔しないための窓配置のポイント

窓の配置で後悔しないためには、以下のポイントを押さえておくことが大切です。
4-1.設計前に隣家の窓の位置を確認する
窓の配置を決定する前に、隣家の窓の位置を確認することは非常に重要です。
これにより、お互いの家が向き合わないようにすることができます。
4-2.窓の高さや形状を工夫する(すりガラス、ルーバー窓など)
すりガラスやルーバー窓を採用することで、プライバシーを守りつつ、視線を遮ることができます。
また、窓の位置を高くすることで、隣家からの視線を防ぐことが可能です。
4-3.バルコニーや洗濯物を干すスペースの配置に注意する
バルコニーや洗濯物を干すスペースが隣家の窓から見えないように工夫することが大切です。
このような配慮があれば、後々のトラブルを避けることができます。
4-4.事前に近隣住民へ説明を行い、納得してもらう
近隣住民への説明を事前に行うことで、トラブルを未然に防ぐことができます。
特に、窓の位置やバルコニーの設置に関する話し合いは重要です。
5.元住宅営業マンまめおやじのアドバイス
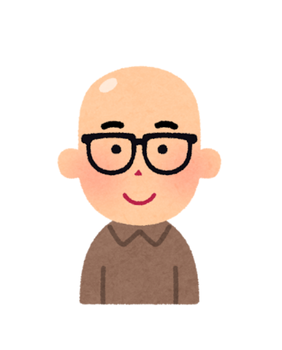
近隣トラブルについて、完全に防ぐことはできませんが、確率を減らすことはできます。
住宅会社、お施主様一緒に解決しましょう。
- 現地測量の際、図面に隣家の窓位置を記入
- 施主様には、法的に問題なくても配慮は必要と説明する
- 給湯器、エアコン室外機も同様
- 問題が起きたら、お施主様、住宅会社で一緒に対応

隣の窓を確認して中庭作ったよ!
6. まとめ:家づくりは計画的に!
家を建てる際には、デザインや間取りだけでなく「隣家との位置関係」も考慮することが大切です。
窓の配置はプライバシーの確保だけでなく、近隣トラブルを防ぐ重要なポイントになります。
施工会社にとっても、こうしたトラブルが起きると施主様との信頼関係にも影響を与えます。
事前の打ち合わせや法律のチェックを怠らず、快適に暮らせる家づくりを心がけましょう。
家づくりは計画的に進めることが大切です。隣家とのトラブルを未然に防ぐために、設計段階からの配慮が必要不可欠です。
しかし、配慮ばかりに気を取られると、希望の間取りやデザインに影響することもあります。
バランスがとても大事になります。
プライバシーを守りつつ快適な住環境を実現しましょう。
家づくりは正解が一つではありません。
本記事の内容が、後悔のない判断をするための参考になれば幸いです。
筆者の考え方や立ち位置については当ブログについて
にまとめています。
ここまで読んで頂きありがとうございました。
あなたにとって良い一日を~まめおやじ


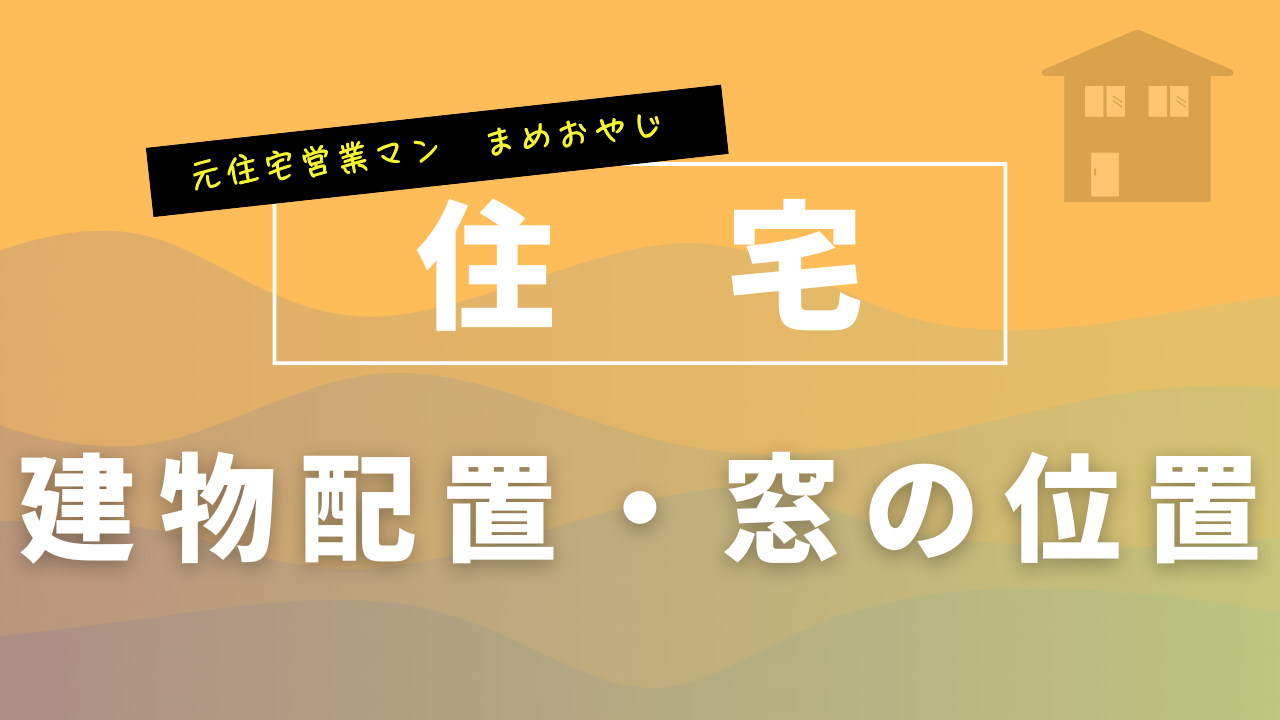
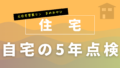
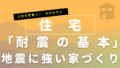
コメント