元住宅営業マンとして約34年間、ハウスメーカー・工務店・不動産開発の現場に携わってきました。
本記事は、営業現場と自宅建築の両方を経験した筆者が、実務経験に基づき家づくりに関する判断材料となる情報を提供することを主な目的としています。
記事内にはPR・アフィリエイトリンクを含む場合がありますが、特定の商品やサービスの購入を推奨・強制するものではありません。
こんにちは。
元住宅営業マンまめおやじです。
「新築の火災保険って、どこで入ればいいの?」「地震保険って必要なの?」
家づくりが進む中で、火災保険・地震保険のことは後回しにしがち。
でも、実は家を建てるときに最も重要なお金の備えのひとつなんです。
本記事では、元住宅営業マンの視点から、保険の基本から損しない選び方、意外な落とし穴までをわかりやすく解説します。
- 注文住宅を建てる予定で、保険について知識がない方
- 火災保険・地震保険の違いや必要性がよくわからない方
- ハウスメーカーから勧められた保険が本当に良いのか不安な方
- 少しでも保険料を安くしたい・補償内容を見直したいと思っている方
- 火災保険にトイレ詰まりや鍵のトラブルも補償されるのか気になる方


1. 【結論】保険は「必須」だけど、内容で差がつく!

注文住宅を建てる際、火災保険はほぼ必須になります。
住宅ローンを借りるとき、金融機関から「火災保険に加入してください」と言われることが多く、実際には加入しない選択肢はありません。
そして、地震保険は任意ですが、日本は地震大国。南海トラフ地震などの巨大地震が心配される今、加入しておいたほうが安心です。
ただし注意したいのは、「とりあえず入ればOK」ではないということ。
保険の内容や補償の範囲によって、保険料もカバーできるリスクも大きく変わってきます。
火災保険・地震保険でチェックすべきポイント
- 火災だけでなく、風災や水災も対象にするか?
- 地震保険をセットでつけるか?
- 家財(家具・家電など)の補償は必要か?
- 子どものいたずらによる破損にも備えるか?
- トイレの詰まりや鍵のトラブルなど、生活サポート付きにするか?
こうした項目は、保険会社やプランによって違いがあるため、自分の家の構造・立地・生活スタイルに合わせた補償内容を選ぶことが大切です。
元住宅営業マンのひとこと

とりあえず入っておけば安心でしょ”は危険です。保険の中身次第で、同じ家でも守られる範囲に大きな差が出ますよ
2. 火災保険の補償範囲は広い
「火災保険」と聞くと、「火事のときの保険でしょ?」と思われがちですが、実はもっと幅広いリスクをカバーできます。
プランによっては、自然災害や日常のトラブルにも対応してくれる、まさに“住まいの総合保険”とも言える内容になっています。
火災保険で補償される主なリスク例
- 火災・落雷・爆発(基本補償)
- 風災・雪災・雹(ひょう)災(台風・強風・大雪など)
- 水災(洪水や土砂災害など)※特約で付ける場合あり
- 水濡れ(上階からの水漏れ・給排水設備の故障など)
- 盗難(窓ガラス破損や家財の盗難)
- 破損・汚損(子どもが家具を壊した、物をぶつけた等)
また最近では、以下のような生活トラブルへの駆けつけサービスが付いている保険も増えています。
よくある付帯サービスの例
- トイレや排水の詰まり対応
- 鍵をなくしたときの開錠・交換
- ガラスが割れたときの応急修理
- 電気設備の不具合対応
★「トイレの詰まり」についてはこちらの記事もご覧ください。
こうしたサービスが無料または少額負担で利用できるのは、子育て世帯や共働き世帯にとって大きなメリット。
保険の“おまけ”と考えず、実際に使えるサービスかどうかも要チェックです。
元住宅営業マンのひとこと

子どもがテレビにおもちゃを投げて壊した”っていう話、本当にあるんです。火災保険の破損補償があれば自己負担ゼロになることは結構ありましたよ
3. 建物の構造で火災保険料が変わる

火災保険の保険料は、家の大きさや補償内容だけでなく、建物の構造によっても大きく変わります。
一般的に、火災に強い構造の方が保険料が安くなります。
例えば、鉄骨造やコンクリート造の家は燃えにくいため、木造よりも保険料が安く設定される傾向があります。
ただし、木造住宅でも「省令準耐火構造」に対応していれば、火災に強いと判断され、保険料が約半分になることもあります。
建物構造と火災保険の関係
- 木造(一般) → 火災リスクが高いため、保険料が高め
- 省令準耐火構造の木造住宅 → 火災に強く、保険料が3〜5割安くなることも
- 鉄骨・RC造 → 燃えにくく、保険料は比較的安い
省令準耐火構造は、建築基準法に基づいた防火性能の高い住宅で、多くのハウスメーカーの注文住宅が標準で対応しています。
これを知らずに「木造=高い」と思い込んでいると、損する可能性もあります。
元住宅営業マンのひとこと

木造のローコストの会社は省令準耐火はオプションのケースが多いですね。追加金額は結構アップしますよ。
4. 地震保険は耐震等級で割引される

地震保険は、火災保険とセットで加入するタイプが一般的です。
建物や家財が地震・噴火・津波で損害を受けた場合に補償されます。
「地震保険に関する法律」により、地震保険の保険金額は火災保険の保険金額の30~50%で設定することになっており、地震による損害を100%カバー(全額補償)することができません。
★地震による損害を100%カバーする特約もあります。
注目したいのが、「耐震等級」による割引制度です。耐震性能が高い建物は、保険料が大幅に割引される仕組みになっています。
耐震等級別の割引率(※2025年5月時点)
- 耐震等級3(最高等級):50%割引
- 耐震等級2:30%割引
- 耐震等級1:10%割引
- 等級なし/旧耐震基準:割引なし
注文住宅では、耐震等級2〜3を取得することが多く、地震保険料もかなり安く抑えることができます。
また、長期優良住宅やフラット35Sなどの認定を受けた住宅であれば、耐震等級が証明されているので、割引もスムーズに適用されます。
元住宅営業マンのひとこと

カタログの耐震3相当と書いてあるだけでは、割引できません。長期優良住宅や住宅性能評価書の取得が必要です。費用がかかりますよ。
補足:地震保険料の低いエリアの場合、そんなに差がでない場合があります
★「長期優良住宅」についてはこちらの記事もご覧ください。
★「フラット35」についてはこちらの記事もご覧ください。
5. 家財補償をどうするかが悩みどころ

火災保険には、「建物だけでなく、家の中の家具・家電などを守る“家財補償」もオプションでつけられます。
とくに子育て世帯は、家財のトラブルが意外と多いです。
家財補償の対象になるもの例
- テレビ、冷蔵庫、パソコンなどの電化製品
- ソファ、ベッド、テーブルなどの家具
- 洋服、食器などの日用品
- 子どもがおもちゃを投げて壊したテレビや窓ガラス
「子どもがいたずらしてテレビを壊した…」「家具の角にぶつかって壁が破れた…」というような、日常で起こりがちな事故にも補償が効くことがあります。
ただし、補償内容や限度額は保険会社によって異なるので、必要最低限に絞るか、しっかりカバーするかを考えるのがポイントです。
元住宅営業マンのひとこと

お子さんがいる家庭は、絶対に家財補償を検討した方がいいです。“え、これも補償されるの!?”という声、よく聞きました。
6. 年末調整で保険料控除になる?

火災保険や地震保険に入ったら、気になるのが「税金の控除対象になるかどうか」です。
実は、火災保険の保険料は控除の対象外です。残念ながら、年末調整や確定申告で還付は受けられません。
しかし、地震保険に関しては「地震保険料控除」の対象になります。
地震保険料控除の概要(2025年5月時点)
- 年間支払った地震保険料のうち、最大5万円まで所得控除できる
- 所得税・住民税の負担が軽くなる
- 火災保険と地震保険をセット契約していても、対象は地震保険部分のみ
特に所得が高めの世帯では、控除の効果が大きくなります。保険料の領収書や契約証明書は大切に保管しておきましょう。
元住宅営業マンのひとこと

火災保険は控除ナシ、地震保険は控除アリ。意外と忘れがちなので、保険証券を年末まで捨てないでくださいね
7. 保険期間と一括払い・年払いの違い
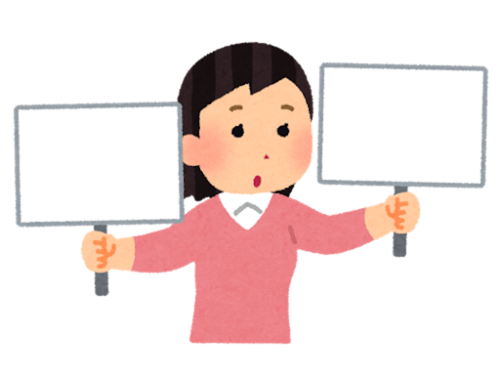
火災保険や地震保険には、保険期間を何年にするか、そして保険料を一括で払うか、毎年払うかの選択があります。
2022年の制度改正により、火災保険の最長契約期間は「5年」となりました。以前は10年契約もできましたが、現在は最長5年です。
支払い方法の違い
- 一括払い(5年分まとめて)
→ 年払いより割安になることが多い
→ まとまった出費になるが、長期的にはお得 - 年払い(1年ずつ支払い)
→ 初期負担が少ない
→ 毎年見直しがしやすい(補償の変更が可能)
火災保険料は住宅ローンと一緒に払うことも可能ですが、一括で払った方がトータルでは安くなるケースが多いため、資金に余裕がある方はぜひ検討してみましょう。
元住宅営業マンのひとこと

ローンに組み込んだから気づかなかったけど、5年で数万円違うなんて…という声、結構ありました。払えるなら一括がおすすめ
8. 保険金が出るケース・出ないケース

火災保険や地震保険は、何でも補償してくれるわけではありません。補償内容をよく理解しておくことが大切です。
保険金が出る主なケース
- 火災、落雷、風災、雪災、水災などの自然災害による被害
- 台風で屋根が飛んだ
- 洪水で床上浸水した(※水災補償をつけている場合)
- 子どもがおもちゃを投げてガラスやテレビを割った(家財補償をつけている場合)
- 隣家の火事が原因で被害を受けた(もらい火も対象)
保険金が出ない主なケース
- 経年劣化や老朽化による損傷
- 手入れ不足による腐食やカビ
- 故意の破損(自分で壊したなど)
- 地震による損害(※火災保険単体では対象外。地震保険が必要)
また、トイレが詰まった、水漏れしたなどの住宅トラブルについては、保険金は出ませんが、次で紹介するような「付帯サービス」で対応できることもあります。
元住宅営業マンのひとこと

雨漏りしても保険出ないんですか?”とよく聞かれました。老朽化によるものだと対象外。保険=万能ではないんです
9. 火災保険の意外なサービスとは?

火災保険に加入すると、補償以外にも“困ったときのサポートサービス”が無料でついてくることがあります。
これは保険会社によって違いますが、次のようなトラブルに対応してくれることが多いです。
よくある付帯サービスの例
- トイレのつまり・水漏れ(作業員が駆けつけてくれる)
- 鍵の紛失・玄関の開錠
- ガラスが割れたときの応急処置
- 排水口のつまりや水道トラブルの対応
- 簡易な修理・点検サービス(年に1回無料など)
これらは「無料駆けつけサービス」などと呼ばれ、利用回数に制限があることもありますが、うまく活用すれば非常に便利です。
火災保険というと「万が一の災害のため」だけのイメージがありますが、日常のちょっとしたトラブルにも頼れる存在になることがあります。
元住宅営業マンのひとこと

「火災保険でトイレ直してもらえた!」と感動する方も多いです。保険証券に記載されてる番号、冷蔵庫に貼っておくのおすすめです!」
★「トイレの詰まり」についてはこちらの記事もご覧ください。
10. 火災保険・地震保険はどうやって選べばいい?

いざ保険に入ろうとすると、「どこで入ればいいの?」「補償ってどれを選べばいいの?」と迷ってしまう方も多いはずです。
火災保険・地震保険は、補償内容・金額・サービスのバランスを見て選ぶことが大切です。
選び方のポイントはこの5つ!
- 補償範囲が生活に合っているか
→ 洪水リスクがある地域なら「水災補償」は必須です。 - 地震保険を付けるかどうか
→ 持ち家でローンがあるなら、地震保険の加入は強くおすすめ。 - 家財補償をつけるか
→ テレビ・家具・冷蔵庫・パソコンなど、大事な家財があるなら検討を。 - 免責金額の設定
→ 小さな損害は自己負担にする代わりに、保険料を安くできます。 - 保険会社の信頼性とサポート体制
→ 万一のとき、しっかり対応してくれるか。口コミも要チェックです。
加入方法はいろいろ
- 住宅会社・工務店経由での加入
→ 手間が少なく、住宅の構造をもとに最適なプランを選んでくれる
→ ただし、料金が高めになることも。見積比較がおすすめ - 自分でネット申し込み・代理店経由
→ 保険料を比較しながら選べる
→ 補償内容をしっかり確認する必要がある(知識が必要)
元住宅営業マンのひとこと

高い保険に入ると保険会社が儲かるだけです。必要な保障を見極めてから入りましょう。
「保険料比較も大事ですが、災害が起きたときは、支払いが集中するので、なかなか受付してもらえないこともあります。
多く扱っている住宅会社の方が有利です。」
【参考】★「ソニー損保」の見積
【参考】★「SBI損保」の見積
11. まとめ
注文住宅を建てるとき、火災保険と地震保険の加入は避けて通れない大切なステップです。
ただ、「なんとなく住宅会社に勧められるまま…」では、損をしたり、いざというときに補償されない…ということも。
この記事では以下のポイントをお伝えしました。
おさえておきたいポイントまとめ
- 火災保険は住宅ローンの条件にもなっている重要な保険
- 地震保険は火災保険とセット加入。耐震等級によって割引あり
- 保険料は構造(木造か鉄骨か)や耐火性能(省令準耐火)で変わる
- 補償内容は「必要なものだけ」に絞れば保険料を抑えられる
- 家財補償をつければ、テレビや家具の破損も対象に
- 保険料は一括払いのほうがお得になるケースが多い
- トイレ詰まりや鍵のトラブルに対応するサービス付きもある
- 加入前には、補償内容・金額・保険会社の信頼性をしっかり比較
火災保険・地震保険は、「万が一のため」だけでなく、日々の安心にもつながる備えです。
家が完成してからでは遅いので、早い段階から、しっかり考えて選びましょう。
元住宅営業マンのひとこと
「“保険って面倒だな…”と思いがちですが、選び方ひとつで何万円も違ってくる世界です。
お金のことだからこそ、納得して選ぶ。それが本当の安心です!」
家づくりは正解が一つではありません。
本記事の内容が、後悔のない判断をするための参考になれば幸いです。
筆者の考え方や立ち位置については
当ブログについて
にまとめています。
ここまで読んで頂きありがとうございました。
貴方にとって良い一日を~まめおやじ


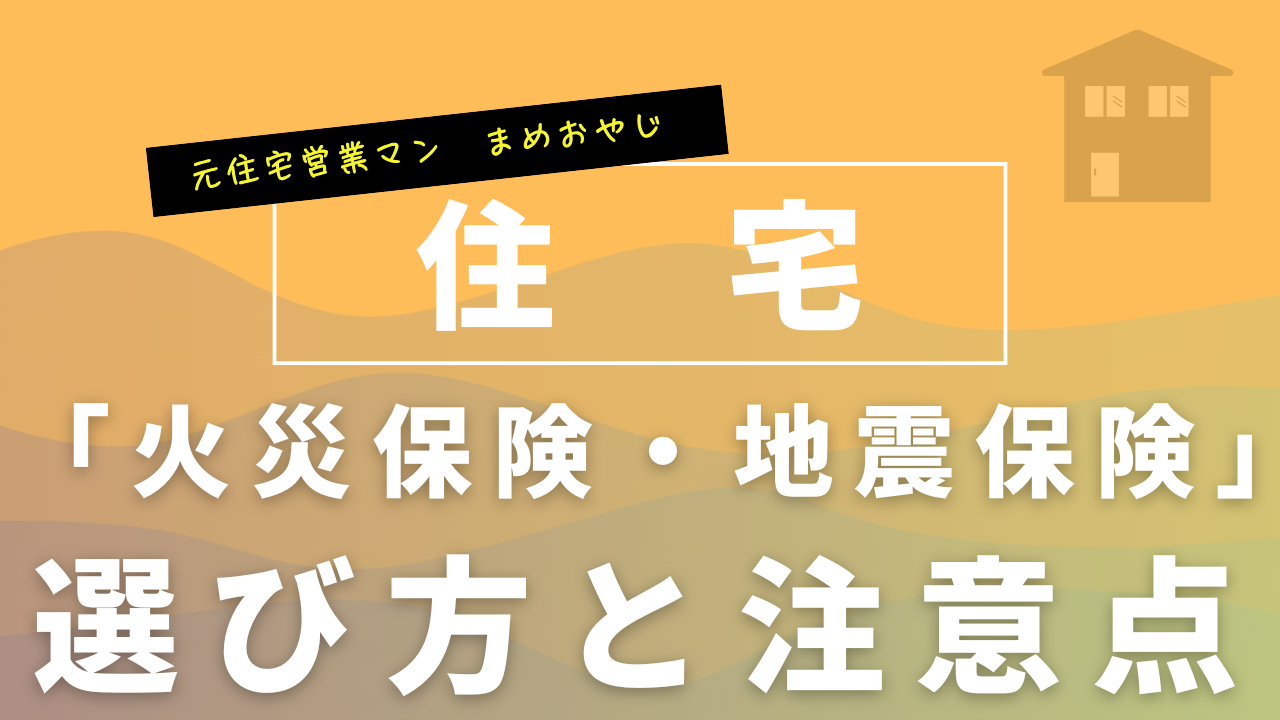

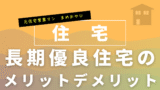



コメント