こんにちは。元住宅営業マンまめおやじです。
外構工事は家の見た目や使い勝手に大きく関わる大切な工事ですが、実はトラブルが多い分野でもあります。
本記事では、実際によくあるトラブルとその対処法、トラブルを未然に防ぐポイントまで簡潔に解説します。
- これから家を建てる人
- 外構工事がまだ決まっていない人
- これから外構工事が始まる人


1.外構工事でよくあるトラブルとは?

外構工事のトラブルは多いです。
- 一般的な外構工事の金額 100~300万
- 請負金額税込500万円以下なら建設業許可が不要
- 極論、だれでも工事ができる
- 施主手配に注意!!
上記に記載のように、極論、だれでも仕事ができるので、どうしてもバラつきがでてしまうのです。
トラブル回避のポイントは以下です。
- 事前の確認
- 近隣への配慮
- 信頼できる業者選び
1-1.施工ミスによるひどい仕上がり
仕上がりが図面と違ったり、傾きや勾配ミスによる水たまりなど、完成後に不満が残るケース。
- 図面と異なる仕上がり
- 勾配ミスで水たまりが発生
- やり直し対応を拒否されることも
1-2.近隣住民とのトラブル事例
騒音や粉塵、工事車両の出入りによる近隣からのクレームが発生しやすい。
- 騒音や振動で苦情がくる
- 車の出入りや駐車で迷惑がかかる
- 無挨拶で印象が悪化
1-3.工事費用の請求トラブル
工事後に「聞いていない追加費用」を請求されるなど、費用面でのトラブルも多い。
- 見積もりより高額な請求
- 勝手な追加工事が行われる
- 契約書の不備が原因になることも
2.トラブル発生時の対応方法
2-1.業者への連絡と対応方法
まずは冷静に連絡し、証拠を残すことで話し合いをスムーズに進める。
- 状況を正確に伝える
- 写真・書面で証拠を残す
- 冷静な対応で感情的対立を防ぐ
2-2.消費者センターへの相談方法
業者との話し合いで解決しない場合は、第三者の相談機関に頼るのも手。
- 「188」に電話で相談可能
- アドバイスや斡旋をしてもらえる
- トラブルの初期段階でも相談OK
188とは↓↓↓
2-3.必要に応じた弁護士への依頼

悪質な業者や金額の大きい損害には、法的対応も検討する。
- 弁護士に相談して対応策を確認
- 無料法律相談窓口を活用する手も
- 書面・証拠の準備が重要
3.トラブル回避のための事前対策
3-1.必要な許可や届出の確認
塀やカーポート設置には建築基準法や条例の制限がある場合も。
- 高さ制限や位置の規制に注意
- 自治体に事前確認する
- 違反すると撤去命令のリスクあり
3-2.近隣挨拶の重要性と心得
近隣との関係悪化を防ぐためには、事前のひと声が効果的です。
基本的に外構業者が行いますが、やらない業者もあります。事前に確認しましょう。
- 工事開始前に簡単なあいさつ
- 工期・時間・内容を簡潔に伝える
- 菓子折り不要でも丁寧な対応を
特に、ご自身で外構業者を手配して注文する際は、要注意です。
3-3.工事中の留意事項と対応
現場でのマナーや管理を業者任せにせず、定期的な確認も大切。
- 材料や機材の置き場を確認
- 作業員の喫煙・騒音対策を伝える
- 気になる点はその場で業者に相談
4.外構工事の業者選びのポイント
4-1.信頼できる業者の見分け方
トラブルの多くは業者選びで決まります。信頼性を見極めましょう。
- 実績・口コミ・対応力をチェック
- 丁寧な説明があるか
- 安さより信頼を重視
4-2.複数業者からの見積もり
相見積もりは、金額だけでなく内容や提案力の比較にも役立ちます。
- 2〜3社から見積もりを取る
- 提案内容や図面も比較
- 安すぎる業者には注意
4-3.業者との打ち合わせ時の注意点
打ち合わせ内容は必ず書面に残し、後の「言った・言わない」を防ぐ。
- 書面・メールで記録を残す
- イメージ図や施工例で共有
- 疑問点は必ず確認
5.まとめ
外構工事でトラブル回避のためのポイントをまとめました。
- 信頼できる業者選び
- 事前の確認
- 近隣への配慮
1.信頼できる業者選び
これにつきます。施工会社と提携している外構業者も安心感はあるでしょう。
一方で先に家を建てた人に紹介してもらうという方法もあります。
2.事前の確認
見積もり・図面は必ず確認。契約書も確認。
工期、支払い方法などお金に関することは必ず書面で確認しておきましょう。
3.近隣への配慮
信頼できる外構業者であれば、近隣挨拶をすると思いますが、必ず事前に確認しましょう。
6.元住宅営業マンからのアドバイス
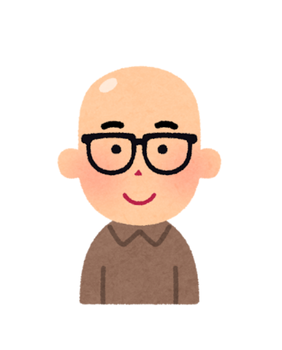
住宅会社と外構業者が分離しているとトラブルの元です。特に施主手配(=ご自身で発注される外構)は施主=新築=外構と事前に連携がカギになります。
1.近隣挨拶
外構工事は施主手配。外構工事に着手後、駐車車両と喫煙等マナー違反で新築施工会社へ苦情の連絡。施主も外構業者は事前に近隣挨拶にいっていなかった。新築施工会社が着工前に挨拶を行っていたため、そこの工事と思われてしまった。
2.設計GL
外構工事は施主の親戚。家の施工会社が設計GL(=家を建てる基準の高さ)を決めます。図面を外構業者へ渡して外構図面と見積もりを作成。その後、GL設定が高くなり、その情報を外構業者へ伝わっていなくて、結果、ブロックの段数が増え、見積もりが当初よりかなりアップした。
3.桝・配管の位置
外構工事は施主の手配。新築の完成間際に業者を決定。外構工事に着手後、桝の位置や、水道メーターボックスの位置がおかしいので、直してもらってくれ、と言われ、外構業者と新築施工会社の板挟みになってしまった。
経験上、施主手配がトラブルが多かったです。どうしても連携不足になってしまいがち。
施主手配の方が、少し安くなる場合があります。一方で、トラブルにならないよう、業者任せにぜず、細心の注意を払いましょう。
★「外構の施主手配」についてはこちらの記事もご覧ください。
元住宅営業マンまめおやじ ブログ:正直住宅コンサルタント 住宅購入や建築に関する正直で実践的なアドバイスを発信中!
ここまで読んで頂きありがとうございました。
あなたにとって良い一日を~まめおやじ


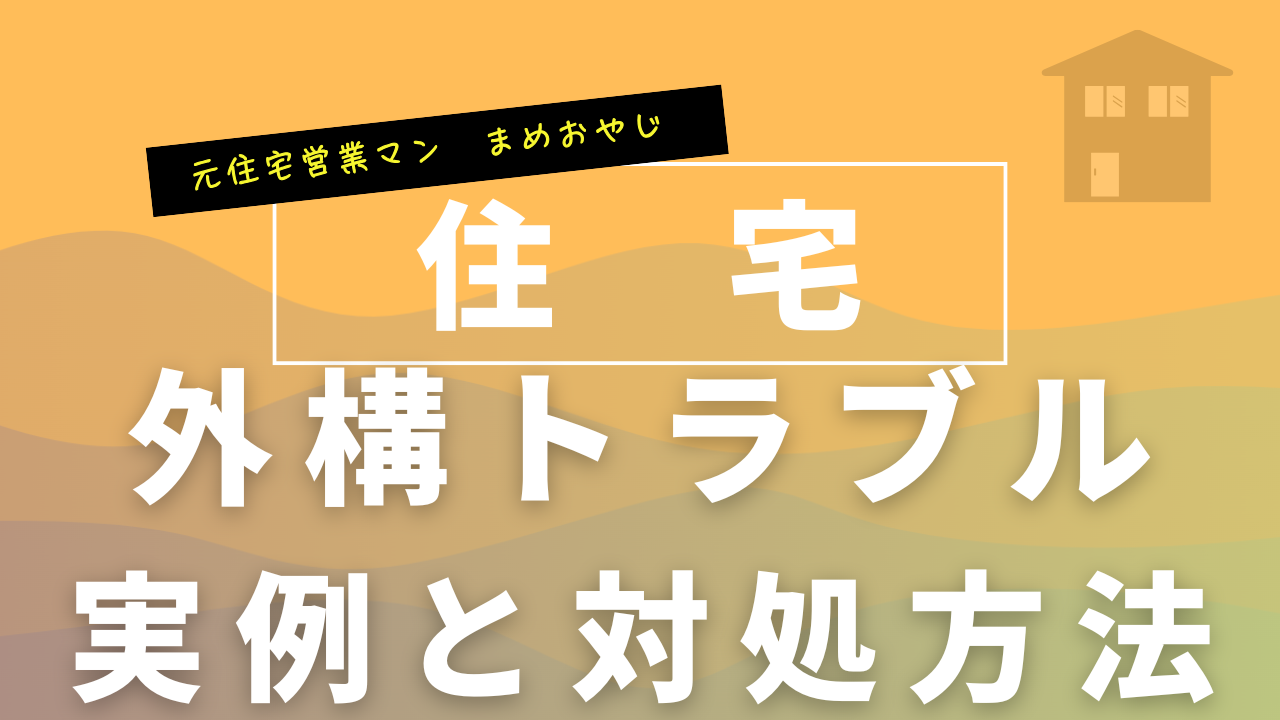

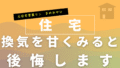

コメント