元住宅営業マンとして約34年間、ハウスメーカー・工務店・不動産開発の現場に携わってきました。
本記事は、営業現場と自宅建築の両方を経験した筆者が、実務経験に基づき家づくりに関する判断材料となる情報を提供することを主な目的としています。
記事内にはPR・アフィリエイトリンクを含む場合がありますが、特定の商品やサービスの購入を推奨・強制するものではありません。
こんにちは。
元住宅営業マンまめおやじです。
住宅を建てたあと、もし不具合が起きたら…誰が直してくれるのでしょうか?
そんなときに重要になるのが「住宅保証」です。
ただし、保証には「対象」「期間」「請求方法」など注意すべきポイントが多く、理解せずにいると、いざという時に「それは保証外です」と言われてしまうケースも。
本記事では、住宅保証の基本から実例までを元住宅営業マンの視点でわかりやすく解説します。
- 住宅保証の基本をわかりやすく知りたい方
- ハウスメーカーや工務店の保証の違いに迷っている方
- 万が一のときに備えて、保証請求の流れを知っておきたい方
- 「保証外だった」という後悔をしたくない方
- 住宅営業マンの実体験を交えて学びたい方


1. 保証内容とは
- 基礎・構造躯体(柱・梁・基礎など)※地盤の傾きを含む
- 雨漏りに関わる部分(屋根・外壁・バルコニーなど)
- 住宅設備(給湯器・換気扇・キッチン・トイレなど)
- 内装・外装の仕上げ部分
■カンタン解説
住宅保証では、まず「何が保証対象なのか」を理解することが大切です。大きく分けると、以下の4つに分類されます。
1.構造躯体などの重要部分(10年保証が義務)
→住宅品質確保法により、基礎や柱などの構造部分は最低10年間の保証が義務づけられています。※地盤の傾きも含む
2.雨漏りに関わる部分
→こちらも10年保証の対象ですが、施工不良かどうかの判断が分かれやすいポイントでもあります。
3.住宅設備部分
→給湯器などはメーカー保証が基本で、1~2年程度が一般的。
4.仕上げ部分
→内装の不具合などは1~2年程度が一般的。外装の不具合の多くは10年ですが、部位やグレード、種類によって大きく異なります。
■元住宅営業マンのひとこと

「全部保証される」と誤解されている方が多いのですが、保証対象は意外と限定的です。
特に内装や設備トラブルは、引き渡し後すぐに気づかないと保証対象外になることもあります。
引き渡し直後は、細かい部分までよくチェックしましょう。
2. 保証期間とは

- 構造躯体・雨漏り:10年(法律で義務)
- 住宅設備:1~2年が一般的
- 内装や外構:保証対象外の場合も
- オプションで延長保証もあり
■カンタン解説
保証は「ずっと続くもの」ではなく、内容ごとに期間の定めがあります。
もっとも重要な構造や雨漏り部分は、新築住宅を建てる事業者に10年間の保証が義務づけられています。
一方で、給湯器や換気扇などの住宅設備の保証は1~2年が一般的で、住宅会社というより設備メーカーが対応します。
保証期間が終わってから不具合に気づいても「すでに対象外」となるので、気になる点は早めに住宅会社へ連絡するのが鉄則です。
■元住宅営業マンのひとこと

引き渡しのとき、「構造体や防水は10年保証ですよ」と説明を受けるのですが、勘違いされる方が多く、すべて10年ではありません。
実際は設備や内装などはかなり短いです。
特にお風呂やキッチンなどの水まわり設備は、最初の1年が勝負。点検時に気になることがあれば、遠慮なく指摘してしましょう。
3. 無償と有償の違いとは?
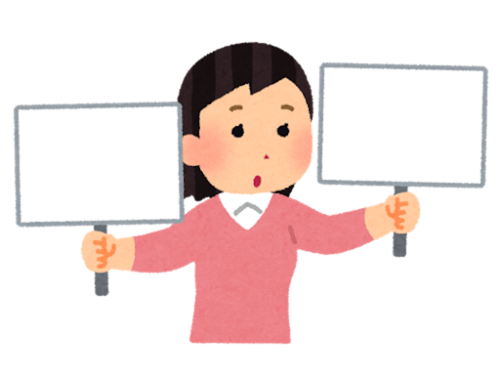
- 無償:保証期間内で住宅会社の責任範囲
- 有償:保証期間外、または自己都合・天災など
- 保証期間内でも有償になるケースあり
■カンタン解説
「保証」と聞くと無料で修理してくれるイメージですが、すべてが無償になるわけではありません。
- 無償保証: 住宅会社やメーカーが責任を負うべき不具合(施工ミス・初期不良など)
- 有償対応: 経年劣化・自然災害・使用方法による破損など
たとえば「ドアが閉まりにくくなった」という症状も、施工の問題なら無償、経年で建具が反った場合は有償になることがあります。
判断基準は会社ごとに異なるため、保証書の内容はしっかり確認しましょう。
■元住宅営業マンのひとこと

お客様から「まだ1年しか経ってないのにお金がかかるの!?」と言われることもよくありました。
でも、生活中のキズや劣化、台風による雨漏りなどは保証の対象外なんです…。
納得できるように事前に「無償・有償の線引き」を聞いておくのがベストです。
4. 保証請求の流れ
- 不具合を発見したら、すぐに住宅会社に連絡
- 担当者または業者が現地確認に来る
- 原因調査(保証対象かどうかを判断)
- 保証対象なら無償修理、有償なら見積もり案内
- 修理・工事の実施
■カンタン解説
「不具合に気づいたらどうすれば?」という方のために、保証請求の一般的な流れを紹介します。
まず、不具合を発見したらすぐに住宅会社へ連絡しましょう(担当者がいれば直接でもOK)。
その後、調査員や下請け業者が現地で確認し、「保証対象かどうか」を判定します。
対象なら無償で修理となりますが、対象外なら「有償になりますが、修理しますか?」と聞かれるのが一般的です。
保証対象外であっても、火災保険を使って修理できる場合もありますので、まずは相談することが大切です。
■元住宅営業マンのひとこと

お客様によっては「壊れてるから当然無料でしょ?」という感覚で怒られる方もいました…。
でも現場を見てみると「使用上の不注意」や「天災による影響」で、有償になるケースも多いんです。
まずは落ち着いて住宅会社に写真を送ったり、連絡を入れましょう。
5. 最大いつまで保証してくれる?

- 法律で定められているのは構造・雨漏りの10年保証まで
- 大手メーカーは20年・30年保証を設定している
- 60年などの長期保証には条件あり(定期点検・有料メンテナンスなど)
- 設備は最長10年の延長保証が主流
■カンタン解説
基本的な住宅保証は、構造や雨漏りなど重要な部分に対して10年までと法律で決められています。
それ以上の保証(たとえば20年保証や30年保証)を掲げている住宅会社もありますが、それはあくまで会社独自のルールです。
長期保証を受け続けるには、「定期点検の受診」や「指定メンテナンスの実施」などの条件付きとなっていることが多く、条件を守らないと保証が失効するケースもあるため注意が必要です。
また、給湯器やコンロなどの住宅設備については、最長10年までの「延長保証プラン」が用意されている場合が多いです(別途有償)。
■元住宅営業マンのひとこと

定期点検の連絡をしても、忙しいからという理由でなかなか受けてもらえず、不具合の連絡が来た時は保証が切れていた、という話がありました。
“保証=自動で続く”ではないので、定期点検の案内が来たら絶対に対応しましょう!
6. 保証延長とは?

- 通常保証(10年)が終了後も、一定の条件で延長可能
- 延長には有償メンテナンスや追加点検が必要なことが多い
- 延長保証は5年単位など段階的に設定されている
- 構造体・防水保証と設備保証は別扱い
■カンタン解説
「保証延長」とは、通常10年で切れる住宅の基本保証を条件付きでさらに延長する制度です。
たとえば、10年目の点検で問題がなければ、有償メンテナンスを行うことで5年間延長できるといった形が一般的です。
多くの住宅会社では、10年・15年・20年と段階的に延長可能な保証プランを用意しています。
ただし、この延長制度は定期点検の記録や推奨される工事の実施が条件となるため、勝手にスルーしていると延長は受けられません。
延長保証があると、長く住む上での安心感が高まりますが、費用や条件面も含めて事前に確認しておくことが大切です。
■元住宅営業マンのひとこと

延長保証は「安心を買う」ようなものです。心配な方は費用はかかりますが、延長するのも選択肢です。
7. 大手・工務店・ビルダーでの違い
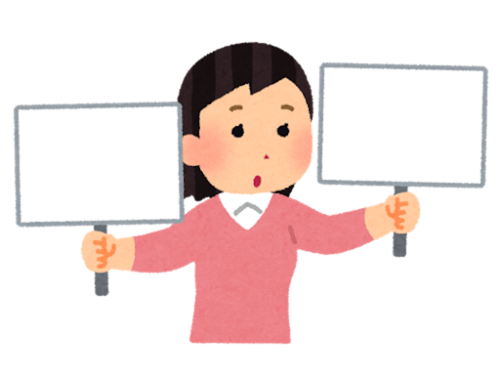
- 大手ハウスメーカーは保証体制が整っていて30年保証も多い
- 地域の工務店は保証年数が短めなことが多い(10年が一般的)
- ビルダー系は会社によって保証内容がまちまち
- アフター対応のスピード・丁寧さにも差が出る
■カンタン解説
住宅保証は、どこで家を建てるかによって内容や対応体制に大きな差があります。
例えば大手ハウスメーカーは、20年・30年の長期保証や自社点検部門を持っているケースが多く、保証の「しくみ」が整っています。
工務店はアットホームで小回りが利く反面、保証は10年のみというところが多い印象です。
ビルダー(ローコスト系など)は、保証やアフターが会社によってバラバラ。
安さの裏にアフターの弱さが隠れていることもあるので、事前確認は必須です。
点検が外注業者かどうかも確認しましょう。
■元住宅営業マンのひとこと

「大手だから絶対安心」とも「工務店は保証が弱い」とも一概には言えませんが、会社によって本当に保証体制は違います。
営業トークだけでなく、書面や仕組みとしてどこまで備えているかを比較してみてください。
★「自宅の5年点検」についてはこちらの記事もご覧ください。
8. 住宅保証の比較ポイントまとめ
- 何年保証されるか?(構造・設備それぞれ)
- 延長できるか?条件は?
- 有償・無償の違いが明記されているか?
- アフターの対応体制(点検・修理受付など)
- 保証書がきちんと発行されるか?
■カンタン解説
住宅保証を比べるときに注目したいのは、「年数」だけでなく中身と条件です。たとえば…
- 20年保証と書いてあっても、有償メンテが前提なら実質の保証とは言えない
- 給湯器やキッチンなど、設備は別契約の延長保証が必要な場合がある
- 万一のときに、誰にどう連絡すればいいか明確か? も重要
■元住宅営業マンのひとこと

「うちは保証ついてますよ!」という言葉だけでは足りません。
地味な作業ですが、保証内容をきちんと比較・理解しておくことも大事です。
9. 保証と火災保険の違い
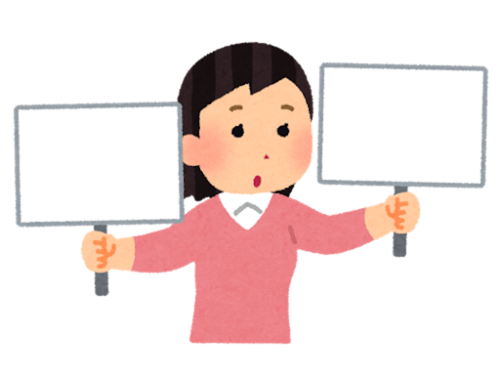
- 住宅保証は住宅の「不具合」に対応(構造・設備など)
- 火災保険は「自然災害や火災による損害」に対応
- 保証は施工不良などが対象、火災保険は事故や災害が対象
- 両方必要だが、対象範囲がまったく違う
■カンタン解説
よく混同されがちですが、「保証」と「火災保険」は役割がまったく別です。
- 住宅保証:建てた会社が責任を持って修理する仕組み(例:基礎にひびが入った、壁が浮いたなど)
- 火災保険:火事・台風・落雷・水害などの災害や事故の損害に対する補償
たとえば、強風で屋根が飛んだら→火災保険
施工ミスで雨漏りしたら→住宅保証
と、原因によって対応が分かれます。どちらか一方だけでは不十分なので、両方そろえておくのが基本です。
■元住宅営業マンのひとこと

お客さんの中には「保証があるから保険はいらないよね?」と言われる方もいます。
でも、自然災害や事故のリスクは保証ではカバーできません。
住宅を守るには、保証と火災保険をセットで考えることが大切です!
10. 工事中に業者が倒産したら

- 工事の途中で倒産すると建築ストップ
- 工事保険に加入しているかがポイント
- 住宅会社によっては保証会社がついている場合も
- 契約書に「倒産時の対応」が書かれているか確認
■カンタン解説
家づくりで一番怖いのが「工事中の倒産」。工事途中で会社が倒産すると、建物は未完成のまま、支払ったお金も戻らない可能性があります。
ただし、以下のような仕組みがある場合は救済されることがあります。
- 住宅会社が完成保証制度(工事保険)に加入している
- 加盟団体(住宅保証機構など)が代わりの施工会社を紹介してくれる
- 契約書に「倒産時の対応」が書かれているか確認済み
事前に確認しておけば、いざという時にも落ち着いて対応できます
ちなみに、住宅瑕疵担保保険というものがあり、住宅会社はすべて加入が義務付けされています。
住宅の引渡し後10年間は構造と防水に部分の瑕疵に対して2,000万円を上限に保証されます。
つまり建てた会社が入居して3年後に倒産していても、5年後に雨漏りした場合、別の会社で保険で修理できるということです。
あくまで引渡し後がポイントですので、ご注意を。
■元住宅営業マンのひとこと

過去に「上棟直後に会社が倒産してしまった…」というケースを見たことがあります。
他の会社が引き継いでくれましたが、追加費用を払う条件で、工事を続行したのを聞きました。
11. 保証されないケースとは?

- 保証期間が終わっている:10年保証の対象が11年目に壊れた場合など
- 経年劣化:使っていれば当然出る傷や痛み(壁紙の変色、ドアの軋みなど)
- 使用者の過失:家具をぶつけて壁が凹んだ、掃除機で部品を壊したなど
- 自然災害の被害:台風や地震による損壊(これは火災保険で対応)
■カンタン解説
「保証があるから安心」と思いがちですが、すべての不具合が保証される訳ではありません。
よくある「保証対象外」は、以下のようなケースです。
これらは原則、自己負担や火災保険での対応になります。
■元住宅営業マンのひとこと

「これも保証してもらえると思ってたのに…」という声、正直よく聞きます。
でも実際は「説明書に書いてある通りに使っていない」だけで保証外になることも。
細かく条件を確認することがトラブル防止の第一歩です!
12. 保証トラブルの実例と対策
■カンタン解説
保証は安心材料の一つですが、「思っていたのと違う」とトラブルになることも。以下、実際にあった例です。
- 例1:壁紙が剥がれてきたが、経年劣化として保証外に
- 例2:エアコンの水漏れが発生 → 保証対象外(施主支給品だった)
- 例3:有償延長をしていないと、10年目からは全額自己負担に
- 例4:「これ保証されると思ってた」とクレーム → 実際は契約書に書かれていなかった
- 例5:外壁の色が薄くなってきた
対策としては…
- 保証書・契約書をしっかり確認し、内容を理解する
- 不安な点は営業マンや現場監督に「これは保証対象ですか?」と聞く習慣を持つ
- メーカー・設備の保証範囲も確認する
- 外壁などは部位ごとに細かく保証内容が決められています。事前に確認しましょう。
■元住宅営業マンのひとこと

保証トラブルって、最初の説明不足と、お客様の勘違いが原因になることが多いんです。
経験上、あまり詳しく説明してくれないので、自分で質問して確認しましょう。
回答はメール等で記録を残すのがベスト。
13. まとめ|住宅保証は“内容の理解”と“確認”が命

住宅の保証制度は、家づくりの安心を支える大切な仕組みです。
しかし、「保証されると思っていたのに対象外だった…」というトラブルは意外と多いもの。
保証期間・保証内容・有償と無償の違い・請求の手順など、事前にしっかり把握しておくことが重要です。
特に注意したいポイントは次の通りです。
- 保証対象は「構造体」「設備」「仕上げ」などで範囲が決まっている
- 保証期間は10年が基本だが、条件付きで延長も可能
- 経年劣化や自然災害、使用者の過失は保証対象外
- 保証制度には「住宅会社の保証」と「火災保険・設備保証」など複数ある
- 工事中の倒産や書類不備によるトラブルも現実に起こる
元住宅営業マンとして感じるのは、「保証はトラブルが起きてからでは遅い」ということ。
ぜひこの記事を参考に、契約前・入居前のチェックをしっかり行い、後悔のない住まいづくりにつなげてくださいね。
家づくりは正解が一つではありません。
本記事の内容が、後悔のない判断をするための参考になれば幸いです。
筆者の考え方や立ち位置については
当ブログについて
にまとめています。
ここまで読んで頂きありがとうございました。
貴方にとって良い一日を~まめおやじ



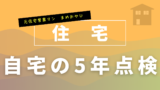

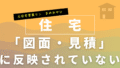
コメント