こんにちは。まめおやじです。土地の売買契約って、なんだか難しそう…
手付金?重要事項説明?引渡し? いつ・何に・いくら必要で、どんなリスクがあるの?
本記事では、住宅営業マンとして土地契約や引渡しに何度も立ち会ってきた筆者が、
初心者にもわかりやすく土地契約の流れと解約時の返金について解説します。
- はじめて土地を購入しようとしている方
- 土地契約で「何にお金がかかるのか」不安な方
- 住宅ローンとの関係や解約時の返金条件が気になる方
- 不動産会社の説明だけでは不安で、事前に流れをつかんでおきたい方
- 元住宅営業マンのリアルな経験談を参考にしたい方


1. 土地を買うステップ|契約までの流れを5段階で解説
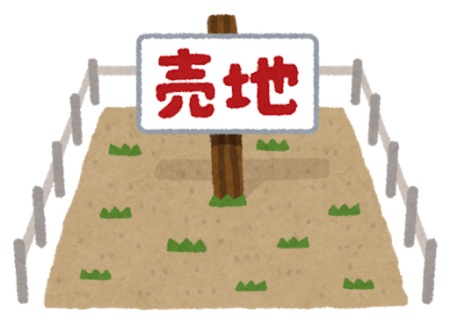
土地を購入する際は、次のような5つのステップで進めていきます。一般的な流れです。
■ 土地購入の5ステップ
- 物件選定
- 購入申込・価格交渉
- ローン特約の確認
- 重要事項説明
- 売買契約の締結
1. 物件選定
まず希望に合う土地探しからスタート。
エリア・広さ・日当たり・地形・周辺環境・建築条件など、総合的にチェック。
2. 購入申込・価格交渉
気に入った土地が見つかったら「購入申込書(買付証明書)」を提出します。
ここで価格や条件の交渉を行うことも可能です。
この時点ではまだ契約ではありませんが、軽い気持ちで申し込むのはNG。あっちもこっちも提出はNG。
3. ローン特約の確認
多くの方が住宅ローンを使って土地を購入します。
ローンが通らなかったときのために「ローン特約」が契約に盛り込まれているかをしっかり確認しましょう。
ローン審査がダメだったときに契約を無条件解除できる大事な仕組みです。
4. 重要事項説明書
契約の前に「重要事項説明書」によって土地の法的・物理的な情報の説明を受けます。
これは不動産会社の宅建士が行います。
境界や接道、再建築可否、水道・下水道の状況など、しっかり確認が必要です。
5. 売買契約の締結
説明内容に納得できたら、いよいよ契約です。
売買契約書に署名・捺印し、手付金を支払います。
ここからは原則キャンセルが難しくなるため、慎重に。契約書の内容をよく読み、不明点は必ずその場で確認を。
▼元住宅営業マンのひとこと

必ず事前に住宅会社に土地を確認してもらうのがポイント
土地を買うのは「見つけたらすぐ契約」ではなく、確認すべきことが多くあります。
★「土地探し」についてはこちらの記事もご覧ください。
2. 契約時に払うお金|契約書を交わすときの費用一覧

土地の売買契約を結ぶ際には、次のようなお金が必要になります。
■ 契約時にかかる主な費用
- 手付金
- 収入印紙代
- 申込金との違い
1. 手付金
契約時に買主(=買う人)が売主(=地主などの売る人)に支払うお金で、通常は売買価格の5%〜10%程度です。
契約を正式に成立させる意味を持ちます。売買代金(=土地の値段)の一部に充当されます。
2. 収入印紙代
売買契約書には印紙税がかかります。契約金額に応じて印紙代は変わり、数千円〜数万円程度が目安です。
契約書は基本2通作成し、双方が1通ずつ保管し、それぞれが自分の分に印紙を貼ります。
3. 申込金との違い
購入申込時に支払った「申込金」は、契約が成立すれば手付金の一部に充当されることがあります。
キャンセル時の扱いは契約前に要確認。「申込金」は法的拘束力がないため、混同しないように注意。
▼元住宅営業マンのひとこと

不動産屋さんが印紙を買ってきて、お金を払うケースもありますよ。
3. その他の費用|意外とかかる追加費用たち

土地購入時は契約金額以外にも、地域や状況によって発生する費用があります。
■ その他にかかる費用一覧
- 水道負担金(不動産屋)
- 自治会費用(不動産屋)
- 下水に関する費用(住宅会社)
- 登記費用(不動産屋)
- 税金の負担(不動産屋)
- 仲介手数料(不動産屋)
1. 水道負担金
自治体によっては、利用権利に対して負担金が求められる場合があります。分担金という場合もあります。
10万〜30万円程度が一般的ですが、地域により大きく異なります。
2. 自治会費用
土地によっては、初回の自治会費や加入金が必要になるケースがあります。
任意加入ですが、地域によっては実質的に“必須”なところも。数百円/月~の年払いが多いでしょうか。
公民館の工事積立金というのもありました。
3. 水道や下水の引込に関する費用
土地に水道や下水が引込されていない場合、引込み工事費用がかかる場合があります。
重要事項説明書には引込が 有・無 という表現になります。
下水がきていない地域だと浄化槽の設置が必要となります。
引込や浄化槽は住宅会社に見積してもらいましょう。
4. 登記費用
土地の所有権移転登記(地主から買う人へ名義を変更する手続き)を行うための登録免許税や司法書士への報酬です。
不動産屋さんが見積をとってくれます。
5. 固定資産税の一部負担
固定資産税は毎年かかるもの。
売主(=地主など売る人)から買主(=買う人)へ名義変更した日を基準に日割り計算する場合が多いです。不動産屋さんに問合せしましょう。
6.仲介手数料
売主(=地主などの売る人)との間に仲介業者が入っている場合必要です。
概ね、物件価格の3%+6万に消費税を足したものです。直接購入する際は不要です。
▼元住宅営業マンのひとこと

購入前に「どんな費用が発生するか」を住宅会社に確認しておくと安心です。
4. 税金の日割り|取得時に発生する日割り清算

土地の売買では、年度の途中で所有権が移転するため、固定資産税等の清算が必要です。
■ 税金清算の基本ルール
- 1月1日基準で売主が負担(一般的)
- 4月1日基準のケースも(地域差あり)
- 月割計算(レアケース)
1. 1月1日割り
基本的にその年の1月1日時点の所有者が、1年分の固定資産税を納税します。
売買時には、引渡し日を基準に買主が日割りで売主へ支払います。
4月1日割りではなく「1月1日割り」が原則です(登記ベース)。
2. 4月1日割り
一部地域では固定資産税の清算を4月1日を起点にすることも。特に関西圏などで見られます。
契約時にどちらの割り方をするか、必ず確認しておきましょう。
▼元住宅営業マンのひとこと

固定資産税が高額だと1月1日割か4月1日割で変わってきますよ。
5. 登記費用について|土地の名義を変えるための費用

土地を購入したら、名義を自分に変える「登記」が必要です。費用の内容や支払い方法はケースにより異なります。
■ 登記費用の種類と支払い方
- 現金で支払う場合
- 住宅ローンを組む場合
- 地目が宅地でない場合
1. 現金で支払う場合
司法書士への報酬+登録免許税をまとめて現金で支払います。合計で10万円〜20万円前後が目安です。
2. ローンを組む場合
上記にプラスして抵当権設定(=土地を担保にとる)費用がかかります。
費用はローン諸費用に含まれます。登記費用を住宅ローンに含めることができる場合があります。
費用目安は土地ローン額(2000万)の0.1%+司法書士の報酬5万~+諸経費なので8万~15万くらいでしょうか。
3. 地目が宅地でない場合
農地や山林の場合、宅地への「地目変更登記」が必要になることがあります。
手間と費用がかかるので、事前確認が重要です。農地の場合は「農地転用許可」も必要になるので要注意。
費用はケースバイケース。司法書士に金額を相談しましょう。
▼元住宅営業マンのひとこと

登記は自分ではやらず、ほとんどの方が司法書士に依頼します。
重要な書類を扱うため、不動産屋さんか住宅会社の紹介が多いですね。
6. 引渡し時に払うお金

いよいよ土地の引渡し。
名義が買う人(=買主)に変わると同時に、大きな支払いが発生します。
■ 引渡しで発生する主なお金一覧
- 引渡しとは?
- 残代金の支払い
- 固定資産税・都市計画税の精算
- 登記費用(最終の精算)
- つなぎ融資を使う場合の流れ
1.引渡しとは?
土地の所有権が売主から買主へ正式に移るタイミングのこと。司法書士が立ち会って、登記変更と支払いが同時に行われます。
2.残代金の支払い
契約時に支払った手付金を除いた「土地代の残金」を振込みで支払います。これで土地の売買が完了します。
3.固定資産税・都市計画税の精算
年額で課税されるため、引渡し日を基準に「日割り計算」で売主と精算します。
例:1月1日基準 → 4月1日引渡しなら、4月1日〜12月/31日分を買主(=買う人)が負担。
4.登記費用(土地)
司法書士へ支払う登記関連費用。
土地の所有権移転登記+住宅ローンを組む場合は「抵当権設定登記」も発生します。
ここでは、土地の場合で、建物が建つと建物分の登記関連費用が別途かかります。予め、全体の登記費用をつかんでおきましょう。
5.仲介手数料
筆者の経験では、引渡し時全額がほとんどでした。契約時に半分払う場合もあります。
6.つなぎ融資を使う場合の流れ
住宅ローンが建物完成後に実行されるタイプの場合、「土地購入時点」ではつなぎ融資を使って一時的に立て替える仕組みです。
つなぎ融資には金利・手数料もかかるため、全体の資金計画に要注意です。
★「つなぎ融資」についてはこちらの記事もご覧ください。
▼元住宅営業マンのひとこと

銀行・不動産屋さん・司法書士と連携がとれていれば、大丈夫。
7. 解約したらお金は戻るの?(返金パターン解説)

土地契約後にやむを得ず解約することになった場合、お金は戻るのか?パターン別に解説します。
■ 解約理由ごとの返金可否一覧
- ローン審査落ちでの解約(ローン特約)
- 停止条件による契約解除
- 天災など不可抗力による解除
- 手付放棄による自己都合解除
- クーリングオフ制度
- 契約不適合による解除
- 債務不履行による解除
- 違約金の実例と注意点
1.ローン審査落ちでの解約(ローン特約)
住宅ローンが本審査でダメだった場合、「ローン特約」により手付金が返金され、無条件で契約解除可能。
※期限内に申告しないとお金が返ってこないことも。
2.停止条件による契約解除
「この物件が●●万円以上で売れなかった場合は契約解除可能」など、あらかじめ定めた条件が満たされなかった場合に契約を白紙解除。
手付金は返金されます。
3.天災など不可抗力による解除
地震・水害など不可抗力によって契約履行が不可能になった場合、手付金が返金されます。
4.手付放棄による自己都合解除
買主(買う人)の都合で辞退する場合、支払済の手付金を放棄すれば解除可能。
詳しくは、こちらをご参照ください。
5.クーリングオフ制度
不動産会社の事務所外(住宅展示場など)で契約した場合、契約書受領から8日以内なら書面で解除可能。
手付金は返金されます。
※売主(=売る人)が個人の場合は適用されません。※宅建登録している住宅展示場は解除できません。
6.契約不適合による解除
土地に欠陥があったり(地中埋設物など)契約内容が違った場合、買主(=買う人)から契約解除できるケースがあります。
7.債務不履行による解除
売主(=売る人)が引渡し期限を守らない、登記に協力しないなどの「重大な契約違反」があれば、買主(=買う人)側から解除・返金請求が可能。
8.違約金の実例と注意点
契約書には「違約時の金銭負担」について具体的な記載があることが多く、
例えば「売買代金の10%を違約金とする」など定められている場合、それに従う必要があります。
▼元住宅営業マンのひとこと

解約理由によって、返金されるか・されないかが大きく変わります。
8. 契約不適合とは?

■ 契約不適合責任とは?
2020年4月の民法改正により、「瑕疵担保責任」に代わって導入されたのが「契約不適合責任」です。
簡単に言うと「契約書で約束した内容と違う状態で引き渡された場合に、売主が責任を負う」制度です。
①わかりやすい事例:配管が図面と違う
図面では「下水管が公道側に接続されている」と記載があったのに、実際には接続されていなかった場合など。
→ 買主(=買う人)は「補修」や「損害賠償」、場合によっては「契約解除」を求めることができます。
②わかりやすい事例:隠れた瑕疵
引渡し後、地下に古い井戸や廃材が埋まっていたなど、目視で確認できない欠陥があったケース。
→ 発見後、一定期間内に申し出れば、契約不適合として対応可能。売主(地主などの売る人)の負担で撤去が原則。
③わかりやすい事例:地盤補強の違い(対象外)
「地盤が思ったより弱かった」「改良費が高くついた」といったケースは、基本的に契約不適合の対象外です。
→ 契約書に「地盤補強費用は買主負担」など記載されているケースが多いです。
▼元住宅営業マンのひとこと

解約になるケースは経験していません。基礎工事の最中に大きな岩とかゴミが出てきた例を数多くありました。
契約不適合は「契約書に書かれていた内容」がすべての判断基準です。
だからこそ、契約書・重要事項説明書は丁寧に読んでおくべきなんです。
9. 元住宅営業マンのアドバイス
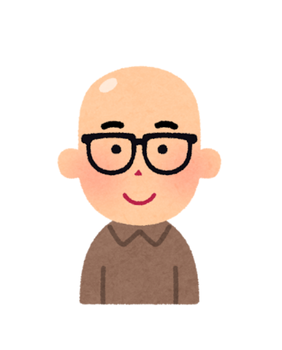
■契約前にやっておくべきこと
- 重要事項説明は契約前にしっかり読む
口頭説明では抜けがち。自宅で何度も読み返すことで、後悔が防げます。 - 住宅営業マンに第三者として見てもらう
宅建業法上、記載がなくても費用に関係することがあるかも。
土地建物セットでみてくれる住宅営業マンの存在は大きいです。
■ 引渡し後に確認すべきこと
- 着工までの土地の管理(草刈りなど)
- 司法書士からの登記完了書類の受取
- 近隣対策(カラーコーンなどの設置)
10. まとめ
- 契約から引渡しまでの流れを理解する
- 土地に関する費用を事前にチェック
- 解約時の返金は条件次第。事前の知識で損しないように
- 住宅営業マンにチェックしてもらおう
知識武装することで、トラブル回避できます。
■ 最後にひとこと
家づくりは大きな決断です。
迷ったときは、一人で抱え込まず、経験ある営業マンや専門家に相談を!
★「営業マン」についてはこちらの記事もご覧ください。
★「建売住宅」についてはこちらの記事もご覧ください。
元住宅営業マンまめおやじ ブログ:正直住宅コンサルタント 住宅購入や建築に関する正直で実践的なアドバイスを発信中!


ここまで読んで頂きありがとうございました。
貴方にとって良い一日を~まめおやじ

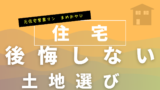

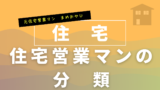
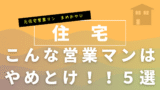
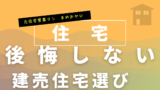

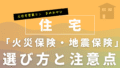
コメント